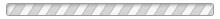胡黄連
(こおうれん)

|
入手時名称:胡黄連 P. kurrooa Royle ex Benth. 撮影場所:富山大学 和漢研 民族薬物資料館 TMPW No.:16210 |
| 生薬別名 | |
| 生薬ラテン名 | Picrorrhizae Rhizoma |
| 生薬英名 | Figwortflower Picrorrhiza Rhizome |
| 科名 | ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae |
| 基原 | - Picrorhiza scrophulariiflora Pennell (IPNI:808412-1) - Picrorhiza kurroa Royle ex Bentham (IPNI:808408-1) |
| 薬用部位 | 根茎 |
| 選品 | 未詳 |
| 主要成分 | 単糖類 monosaccharides - Mannitol (P. kurroa) モノテルペノイド monoterpenoids - Kutakoside (P. kurrooa) - Picroside I (P. kurrooa) - Picroside II (P. kurrooa) - Picroside III (P. kurrooa) - Picroside IV (P. scrophulariiflora) フェニルプロパノイド phenylpropanoids - Kutkin (P. kurrooa) フェノール系化合物 phenol derivatives - Apocynine (P. kurrooa) その他の芳香族誘導体 other aromatic derivatives - Scroside A (P. scrophulariiflora) - Scroside B (P. scrophulariiflora) - Scroside C (P. scrophulariiflora) - Vanillic acid (P. kurrooa) |
| 薬理作用 | 肝保護作用 (picroside II), 抗炎症作用. |
| 臨床応用 | 解熱,解毒,鎮静,健胃,殺虫薬として,小児の驚疳,泄痢,黄疸,痔疾,目の炎症などに応用する. |
| 頻用疾患 | 小児栄養不良による発熱, 下痢, 黄疸, 痔核. |
| 含有方剤 | |
| 帰経 | 心, 肝, 胃, 大腸, 小腸 |
| 性 | 寒 |
| 味 | 苦 |
| 神農本草経 | |
| 中医分類 | 清虚熱薬 |
| 薬能 | 清湿熱,除骨蒸,消疳熱.湿熱瀉痢,黄疸,痔疾,骨蒸潮熱,小児疳熱に用いる. |
| 薬徴 | |
| 備考 | ※ 正倉院薬物の「黒黄連」は胡黄連で, このものの原植物は組織形態学 (内鞘繊維の有無) 及び成分化学 (GC-MSによる比較) 的検討から P. scrophulariifloraであると考えられた. P. scrophulariiflora はネパール, 中国のチベット自治区東南部, 雲南省西北部及び四川省西部に分布する. 『中華人民共和国薬典』収載品はこのものの根茎である. 一方, P. kurroa はインド, パキスタン, シッキム及びネパールなどに分布し, このものの根茎及び根はアーユルヴェーダで「Katuki」と称して黄疸, 消化不良, 発熱に用いられ, さらに現在では急性ウィルス性肝炎や気管支喘息にも応用されている. ※ 胡黄連は正倉院に納められてはいるが, 大変高価で一般には入手不可能であった. そのため日本では代替品を探し, 『証類本草』の附図からセンブリがこのものにあてられた. 室町末期~江戸初期の頃であり, 江戸初期にはそれが誤りであることに気づいている学者もいた. 日本の民間薬としては代表的なセンブリ (当薬) はこうして開発された. ※ 中国東北諸省, 朝鮮半島産の胡黄連はメギ科 (Berberidaceae) のタツタソウ (イトマキグサ) Jeffersonia dubia Benth. の根で 「鮮黄連」 ともいう. 外部リンク: 民族薬物DB, KNApSAcK |
| 参考文献 | 主要成分 C1) 和漢薬百科図鑑 Vol. I, pp. 160-161. C2) 生薬学概論, p. 228. C3) Phytochemistry 47, 537-542 (1998). |